愛犬とベッドで一緒に眠ることに喜びを感じる飼い主さんは少なくありません。信頼する愛犬がすぐそばにいる安心感、温かい体温、規則正しい寝息…これらは、飼い主にとって何物にも代えがたい癒やしとなるでしょう。
しかし、その一方で、
「犬と一緒に寝るのは衛生的にどうなの?」
「小さな子犬や赤ちゃんがいるけど、大丈夫?」
「万が一、事故につながるようなことはない?」
といった不安の声や、「犬と一緒に寝ると死亡リスクがある」といった、ドキッとするような情報を見聞きすることもあります。特に「死亡」という言葉は、飼い主さんにとって最も避けたい事態であり、大きな不安の原因となります。
この記事では、そんな飼い主さんの不安や疑問を解決すべく、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
- 犬と一緒に寝ることの魅力
- 一緒に寝ることに潜むリスク
- 「死亡」リスクの具体的な内容とその可能性
- リスクを最小限に抑え、安全に一緒に寝るための方法
- 一緒に寝る以外の、安全な絆の深め方
この記事を読むと、犬と一緒に寝ることのリスクとメリットを正しく理解し、あなたと愛犬にとって最も安全で幸せな睡眠スタイルを見つけるためのヒントが得られます。大切な家族である愛犬と、そしてあなた自身の健康と安全を守るために、ぜひ最後までお読みください。
執筆者プロフィール

なお
- 薬剤師兼ブロガー
- 資格:
日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師
日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師
一般社団法人薬学教育協議会 認定実務実習指導薬剤師 - 愛犬チワワ:アル(♂)
- プロフィールの詳細はこちらから
愛犬と一緒に寝る人が急増中!その背景とは?

現代社会では、犬を「ペット」ではなく「家族の一員」として迎える家庭が増えています。
あるペット関連企業の調査では、飼い主の約60%が「愛犬と同じベッドで寝る」と回答しており、その理由は「寂しさを紛らわせる」「癒し効果」「安心感がある」など様々です。中には「犬がいないと眠れない」という声も多く、精神的な依存に近い関係性を築いているケースも珍しくありません。
〈添い寝がもたらすメリット〉
- 飼い主のストレス軽減:犬のぬくもりが、安心感を与え、不安や孤独感を和らげる。
- 幸福感の向上:「幸せホルモン」とも呼ばれるオキシトシンが分泌されることで飼い主の幸福感を増進させる。
- 犬とのスキンシップ向上:物理的な接触を通して絆が深まり、信頼関係が強化される。
- 温もりと心地よさ:犬の温もりは特に寒い季節には心地よく、柔らかい毛並みに触れることで安らぎを感じる。
- 犬の情緒安定(特に分離不安の子):飼い主と一緒にいることで安心し、夜泣きや不安行動が減少することも。
- 寝つきが良くなる:規則的な呼吸や鼓動がリズムとなり、深い眠りを促す。
一方で、これらの恩恵はすべて「安全」が前提で成り立つものです。無防備な寝室環境のままでは、思わぬ悲劇に繋がる可能性もあるのです。ペットとの共同生活が当たり前になった今こそ、安心と安全のバランスがより重要になっています。
また、添い寝をすることが犬の生活習慣にどのような影響を与えるのか、しっかりと考えることも必要です。睡眠の質、運動量、日中の活動性など、多方面から見たときに本当に「共寝」が犬にとってプラスなのかを見極めることが大切です。
犬と一緒に寝ることに潜む「死亡」のリスク

「犬と一緒に寝ると死亡リスクがある」という情報は、飼い主さんを非常に不安にさせます。この「死亡」という言葉が具体的にどのようなリスクを指しているのか、そして他の潜在的な危険性について見ていきましょう。
1. 窒息のリスク(赤ちゃん、子犬、小型犬)
これが、「死亡」というキーワードに直結する最も深刻なリスクです。
- 人間の赤ちゃんの場合
- アメリカ小児科学会では、乳幼児と親が同じ寝具で寝ること自体を推奨していません。ましてや、そこに犬が加わることは、窒息やSIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクを著しく高める危険な行為です。
- 飼い主が寝返りを打った際に、意図せず赤ちゃんの上に犬を押し付けてしまったり、犬自身が赤ちゃんの顔の上に寝てしまったり、重い体で圧迫してしまったりする可能性があります。
- 子犬や小型犬の場合
- 体が非常に小さい子犬や小型犬の場合、飼い主が寝返りを打った際に、誤って押しつぶしてしまったり、重い布団の下敷きになってしまったりすることで、窒息や圧迫死に至る可能性があります。
この窒息リスクは、犬と一緒に寝ることにおける最も直接的で重大な「死亡」リスクであり、特に人間の赤ちゃんや非常に小さな犬にとっては現実的な危険です。
2. 人獣共通感染症のリスク
犬から人へ、あるいは人から犬へ感染する可能性のある病気が存在します。一緒に寝るという密接な接触は、その感染リスクを高める可能性があります。
〈細菌感染〉
- パスツレラ菌:犬の口の中に常在している菌。寝ている間に顔などを舐められることで感染する可能性がある。
- カプノサイトファーガ・カニモルサス菌:犬の口の中に常在。就寝中に顔を舐められることで感染の可能性。
- サルモネラ菌、カンピロバクター菌:犬に生肉を与えている場合、犬との接触や糞便を介して感染する可能性がある。
〈寄生虫感染〉
- ノミ・マダニ:散歩で付着したノミやマダニが人を刺し、重篤な感染症(SFTSなど)を媒介する可能性がある。
- 回虫・鉤虫:犬の糞便中に虫卵が含まれている場合、何らかの形で人の口に入ると感染する可能性がある。
- 皮膚糸状菌症:カビの一種で、感染した犬から人へ接触感染する。寝具を介して感染する可能性もあり。
〈その他の感染症〉
- まれに、ブルセラ症、Q熱、エキノコックス症(特定の地域)などのリスクも考えられる。
ただし、健康な成人と、定期的なワクチン接種、ノミ・マダニ・内部寄生虫の駆除・予防をしっかり行っている健康な犬であれば、これらの感染症のリスクは一般的に低いと考えられています。しかし、免疫力が低下している人(高齢者、乳幼児、妊婦、病気治療中の人など)にとっては、リスクが高まるため注意が必要です。
3. アレルギー・喘息の悪化
犬の毛、フケ、唾液にはアレルゲンが含まれており、慢性的なアレルギーを引き起こす原因になります。また、就寝時に長時間接触することで、症状が悪化するケースも見られるので注意が必要です。
鼻水、くしゃみ、目のかゆみ、皮膚の発疹、喘息発作の誘発など
犬アレルギーがないと思っていても、長期間一緒に寝ることで新たに発症する可能性もゼロではありません。
4. 睡眠の質の低下(飼い主・犬双方)
人間と犬では、睡眠のサイクルやパターンが異なります。一緒に寝ることで、お互いの睡眠が妨げられる可能性があります。
- 犬による妨害
- 寝返り・移動:犬も寝ている間に体勢を変えたり、場所を移動することで飼い主が起きてしまう。
- いびき・寝言:犬もいびきをかいたり、寝言を言ったりすることがある。
- 起きる・降りる:夜中に水を飲んだり、トイレに行く際のベッドの上がり降りの物音や振動。
- 体温:犬の体温は高いため、夏場は暑苦しく感じて目が覚めることも。
- 飼い主による妨害
- 飼い主の寝返りやいびきで、逆に犬が安眠できていない可能性がある。
質の高い睡眠が妨げられることで、日中の眠気、集中力低下、イライラ感、免疫力低下など、心身の健康に様々な悪影響が出ます。
5. 行動上の問題を引き起こす可能性
常に一緒に寝ることが、犬の行動に予期せぬ影響を与えることもあります。
〈引き起こす可能性がある行動上の問題〉
- 分離不安
飼い主がいない不安が強まり、留守番時に問題行動(吠え続ける、破壊行動など)を起こす。 - 要求行動の強化
ベッドに上がりたい、撫でてほしいといった要求行動がエスカレートする可能性がある。 - 縄張り意識・攻撃性
ベッドを自分の縄張りと認識し、他者が近づくことを嫌がったり、唸ったり、攻撃的な行動を示すようになる。 - 睡眠中の攻撃性
寝ている時に不用意に触られたり、急に動かれたりしたことに驚いて反射的に噛んでしまう。
6. 怪我のリスク
寝ている間の無意識な動きや、予期せぬ出来事による怪我のリスクもあります。
〈飼い主が負う怪我のリスク〉
- 寝返りを打った際に爪で引っ掻かれる
- 寝ぼけて噛まれる
〈犬が負う怪我のリスク〉
- 飼い主の寝返りで誤ってベッドから落とされる
- 犬自身が寝ぼけてベッドから落ちて怪我をする(特に子犬や老犬)
- 踏まれてしまう(特に小型犬)
これらのリスクを総合的に見ると、「犬と一緒に寝ると死亡する」という直接的な表現は、主に乳幼児や超小型犬の窒息リスクを指している可能性が高いですが、それ以外にも感染症、アレルギー、睡眠障害、行動問題、怪我といった、様々な健康・安全上のリスクが存在することがわかります。
【実例紹介】犬と一緒に寝ることにより起きた「死亡事故」
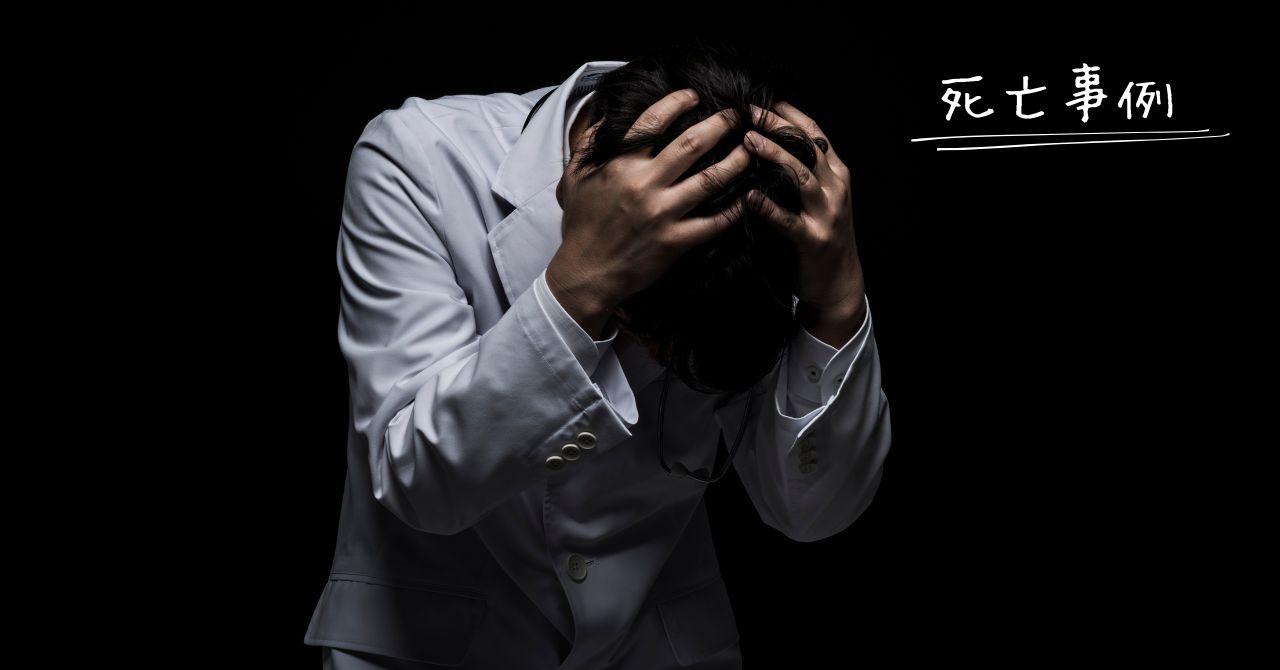
事例①:大型犬が覆い被さり赤ちゃんが窒息死
ある家庭では、生後6ヶ月の赤ちゃんとラブラドール・レトリバーが一緒にベッドで寝ていました。深夜、犬が赤ちゃんの体に覆い被さる形になり、赤ちゃんは窒息。
この事故は、わずか数分間の出来事でした。赤ちゃんの呼吸が止まり、発見されたときにはすでに手遅れ。両親は深い悲しみに包まれ、その後「動物との添い寝は十分な配慮が必要」とメディアで訴えるようになりました。
事例②:寝返りで小型犬を圧迫死
高齢の男性がチワワと一緒に布団で寝ていたところ、夜中に寝返りを打ち、犬を押し潰してしまったという事故も発生しています。
寝ていたため気づかず、朝になって愛犬の遺体を発見し、深いショックを受けた男性は「こんなことになるとは思わなかった」と涙ながらに語りました。
事例③:ベッドからの転落による頸椎損傷
チワワが飼い主と添い寝中に、ベッドから落下して首を打ち、数日後に死亡するという痛ましい事故も報告されています。
高さのあるベッドからの転落は、小型犬にとっては致命的な怪我を負うことがあり、特に骨が未熟なパピーやシニア犬は要注意です。
これらの事故は決して他人事ではなく、誰にでも起こりうる現実です。愛犬との心温まる時間が、取り返しのつかない事態にならないためにも、リスクを「見える化」することが重要です。
死亡事故を防ぐ!愛犬と一緒に寝る上で気を付ける10のポイント

様々なリスクを理解した上で、それでも「愛犬と一緒に寝たい」と考える場合、そのリスクを可能な限り低減するための対策を講じることが不可欠です。
- 衛生管理の徹底
- 犬と飼い主の健康管理
- 物理的な安全確保
- 適切なしつけと関係性
〈愛犬と一緒に寝るための注意点と対策〉
- 人間の赤ちゃんと一緒に寝るのは絶対に避ける
- 子犬・超小型犬との添い寝は慎重に検討する
- 窒息・圧迫のリスク、飼い主の寝相、寝具の種類、犬のサイズなどを十分に考慮した上で検討する。
- 犬の性格を考慮する
- 性格:神経質、怖がり、攻撃的、縄張り意識が強い犬は、一緒に寝るのに向いていない可能性がある。
- 飼い主と犬の健康状態を考慮する
- 飼い主:免疫力が低下している人、重度のアレルギーや喘息を持つ人、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害がある人は、一緒に寝るのを避けるか、医師に相談する。
- 犬:関節炎、皮膚病、高齢犬などは、専用のベッドで寝かせてあげる方が良い場合もある。
- 定期的な獣医ケアを欠かさない
ワクチン接種(混合ワクチン、狂犬病ワクチン)、寄生虫対策(ノミ・マダニ駆除薬、フィラリア予防薬、内部寄生虫駆除薬)、健康診断など健康管理を欠かさず行う。 - 徹底した衛生管理を実践する
- 犬のケア:定期的なシャンプー、ブラッシング、爪切りを行う。散歩後は足裏をきれいに拭く。
- 飼い主のケア:寝る前や、犬に触れた後は手洗いをする習慣をつける。
- 寝具のケア:布団・シーツは週に1回以上洗濯し、ダニや細菌の繁殖を防ぐ。
- 寝床の工夫で物理的な距離と安全を確保する
- ベッドの高さを低くする:ベッドの高さを低めに調整し、落下しても怪我をしにくい環境にする。
- 犬用スペースを作る:犬専用のブランケットやスペースを用意し、寝床の境界を明確にする。
- 落下防止:落下防止のガードやクッションを設置し、物理的な対策を徹底する。
- 睡眠環境を整える
- 寝室の温度・湿度を適切に保つ。
- 寝具は、犬の爪が引っかかりにくい素材を選ぶなどの配慮を行う。
- 適切なしつけとルール設定
- コマンドの習得:「降りて」「ハウス」「待て」などの基本的なコマンドを教え、飼い主の指示に従えるようにしておくことが重要。寝る時以外のベッドへの乗り降りを許可制にするなど、ルールを明確する。
- 資源防衛のチェック:ベッドの上で唸る、歯をむき出すなど、縄張りを守るような行動の有無確認・修正。
- 寝返りセンサー・見守りカメラの導入で夜間の異常を早期発見
これらの対策を講じても、リスクを完全にゼロにすることはできません。常に「もしも」の可能性を考え、安全を最優先する姿勢が大切です。
アレルゲンとなる犬の毛やフケへの対策に関しては以下の記事で詳しく解説しました。愛犬の衛生管理を徹底し、一緒に寝ることによる死亡リスクを少しでも減らしていきましょうね。
チワワの毛が抜ける原因は換毛期?病気?抜け毛がひどい時の対策を解説!
愛犬と一緒に寝るだけが愛情じゃない!安全な絆の深め方

一緒に寝ることにリスクが伴うことを理解し、「やっぱり安全を優先したい」と考える方もいるでしょう。
しかし、一緒に寝なくても、愛犬との間に深い絆を築き、愛情を伝える方法はたくさんあります。
〈添い寝以外での安全な絆の深め方〉
- 同じ寝室で、別の寝床で寝る
飼い主のベッドのすぐそばに、愛犬専用の快適なベッドを用意してあげましょう。お互いの存在を感じながら、それぞれのスペースで安心して眠ることができます。 - 日中のスキンシップを大切にする
起きている時間に、意識的に愛犬と触れ合う時間を増やしましょう。ソファで隣に座って撫でる、抱っこする、マッサージをするなど、愛情のこもったスキンシップは、犬に安心感と幸福感を与えます。 - 質の高い遊びや散歩の時間を作る
一緒に楽しく遊んだり、散歩中にコミュニケーションを取ったりすることは、信頼関係を築く上で非常に重要です。単に運動させるだけでなく、飼い主が愛犬に注意を向け、関わっていることを示すことが大切です。 - トレーニングや学習
一緒に何かを学び、達成する経験(おすわり、ふせなど)は、飼い主と犬の間のコミュニケーションを深め、信頼感を高めます。褒めてしつける方法で行いましょう。 - リラックスできる環境を提供する
愛犬が安心してくつろげる、静かで快適な居場所を用意してあげることも、愛情表現の一つです。
一緒に寝るという行為だけが、愛情の深さを測るものではありません。日々の生活の中で、愛犬の心と体の健康に気を配り、様々な形でコミュニケーションをとることが、真の信頼関係と深い絆を育むのです。
まとめ:愛犬と一緒に寝るリスクを理解し、賢明な判断を

愛犬と一緒に寝ることは、多くの飼い主にとって大きな喜びですが、同時に様々なリスクも伴います。
- 犬と一緒に寝ることで、特に人間の赤ちゃんや超小型犬の窒息・圧迫事故を引き起こす危険性がある。
- 人獣共通感染症、アレルギー、睡眠の質低下、行動上の問題、怪我などのリスクが存在する。
- これらのリスクは、衛生管理、健康管理、寝床の工夫、しつけなどによって、ある程度低減することは可能。
- しかし、これらを行ってもリスクを完全にゼロにすることはできない。
- 同じ寝室で別の寝床で寝るなど、一緒に寝なくても犬との関わり方で絆は十分に深められる。
最終的に、愛犬と一緒に寝るかどうかは、飼い主さん自身の判断に委ねられます。しかし、その判断は、「可愛いから」「自分が寂しいから」といった感情だけでなく、考えられるリスクを十分に理解し、愛犬と自身の健康と安全を最優先した上で、冷静に行われるべきです。
もし、一緒に寝ることを選択するのであれば、この記事で紹介した安全対策を徹底し、常に状況を観察し、何か問題があればすぐに対応できるようにしておきましょう。そして、少しでも不安がある場合や、判断に迷う場合は、必ずかかりつけの獣医師や、信頼できるドッグトレーナーに相談してください。
愛犬との暮らしは、喜びと責任の両方を伴います。正しい知識に基づいた賢明な判断で、あなたと愛犬にとって、最も安全で幸せな形を見つけてくださいね。
